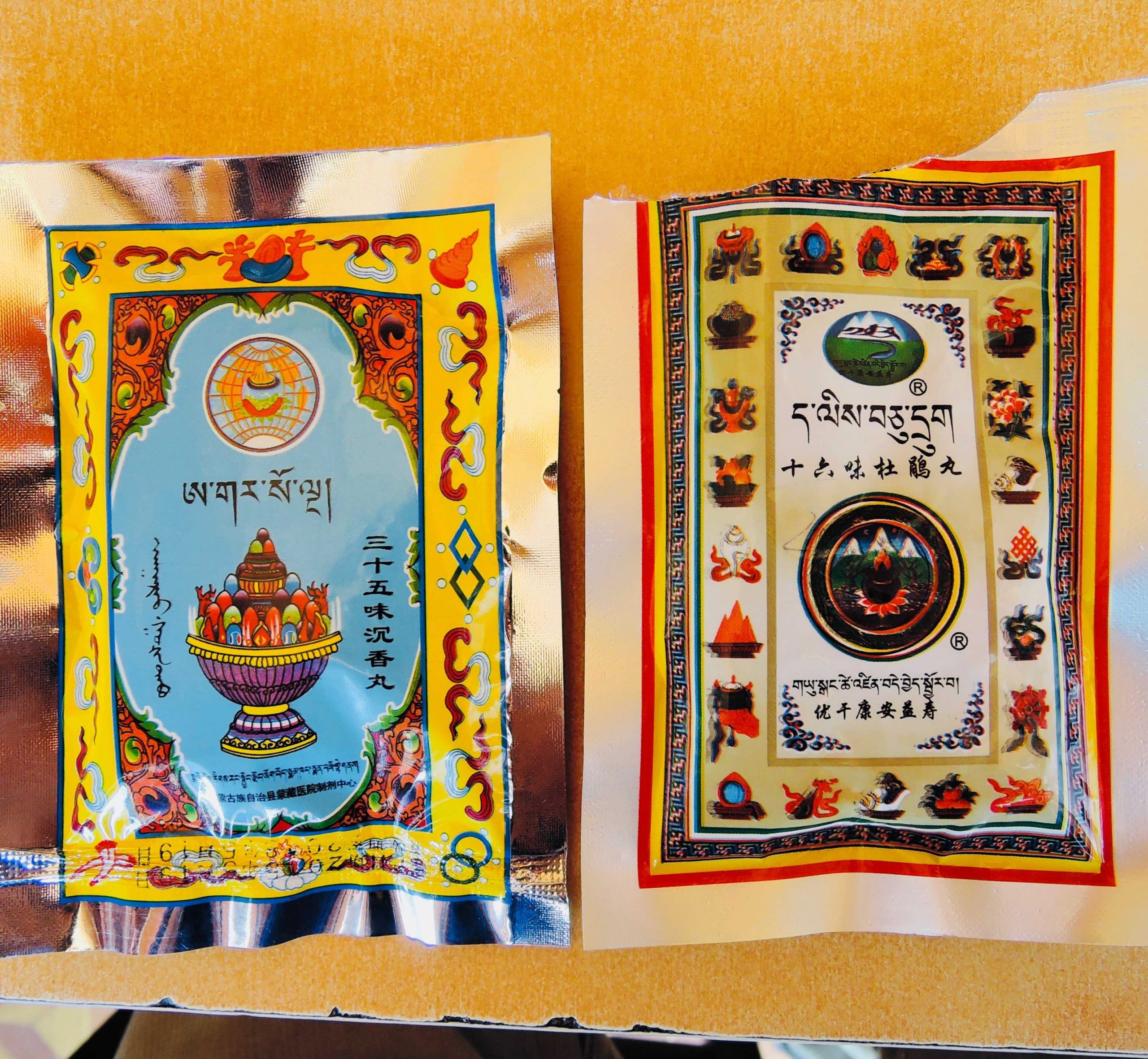山芋(ながいも)のことです。薬物としての山芋はカラカラに乾燥させられ、またでんぷん質が固まって非常に硬く、白色です。滋養強壮の作用が有り、東洋医学の五臓六腑では肺、脾、腎に対して作用します。「益気養陰、補脾肺腎」と表現されます。陰と陽のうち陰に作用し、体の気を充実させるところにあります。そこから以下の場合で応用されます。
1.体の疲れ、食欲不振、下痢、消化不良など。
2.空咳など、痰が多くない咳をよくする。
3.頻尿、男性の夢精、女性の「おりもの」の量が多いなど泌尿器系の病気。腎の気を補う性質から以上のような病気に効果を発揮します。泌尿器関係で体から出るものが異常に多いのは、中医では一般に「気」が不足して、それらの分泌をとめることができないからと解釈し、特に腎の働きとは切り離すことはできません。そこで腎の気をダイレクトに補うことのできる山薬はもってこいというわけです。
4.のどの渇きに。陰を補うという性質から、陰が不足して陽が盛んになるタイプのいわゆる糖尿病にも使われます。
- ホーム
- ブログ
- ダイエット・食・薬膳・漢方茶
- 山薬(さんやく)